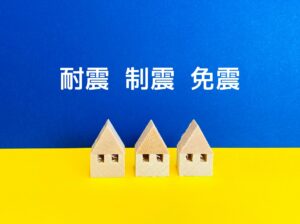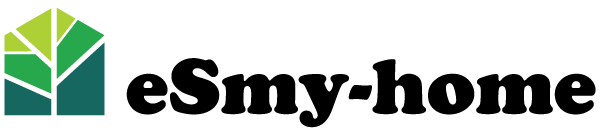
マイホームの購入は、多くの人にとって人生で最も大きな買い物のひとつです。住宅ローンの返済計画や火災保険の加入については入念に検討する方が多い一方で、「地震保険」については十分に理解されないまま契約されているケースが少なくありません。
「本当に必要なのか?」
「保険料が高そうだから最小限でいいのでは?」
そう考える方も多いでしょう。しかし日本は世界でも有数の地震多発国です。実際、世界で発生するマグニチュード6以上の地震のうち、約2割は日本周辺で起きているといわれています。
阪神淡路大震災(1995年)、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)など、私たちはこれまで繰り返し大地震を経験してきました。そのたびに多くの住宅が全壊・半壊し、生活基盤を失った人々が経済的に追い詰められました。そうした状況から人々を守るために作られたのが「地震保険」です。
本記事では、地震保険の歴史や仕組み、火災保険との違い、住宅購入時の考え方、さらに割引制度や「耐震等級3の住宅でも必要なのか?」という疑問に触れ、丁寧にご紹介していきます。
地震保険はいつ?どんな目的で始まったのか
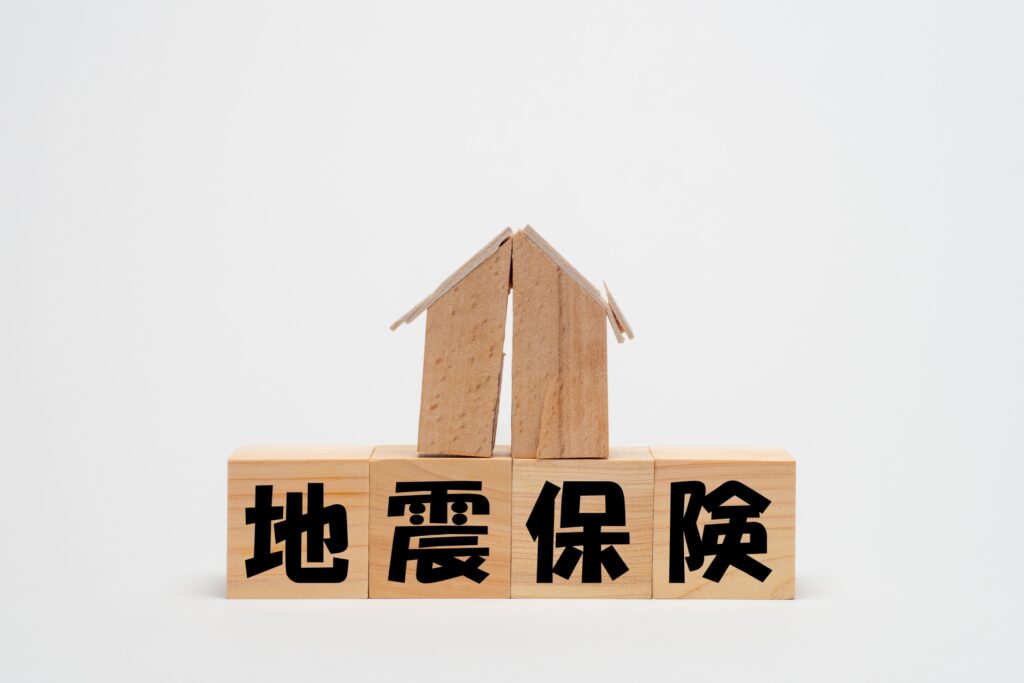
地震保険が誕生したのは1966年のことです。戦後の復興が進み、住宅を持つ人が増えた高度経済成長期、日本政府と損害保険会社は「地震による被害をどうカバーするか」という課題に直面しました。地震による被害は一度に膨大な規模に及ぶため、民間の保険会社だけでは支えきれません。そこで国と民間損保が共同運営する仕組みとして制度化されました。
地震保険は 大地震によって住宅や家財が失われたときに、生活再建のための経済的打撃を和らげることを目的としています。つまり、建物を元通りにする「完全補償」を目指したものではなく、生活を立て直す「必要最低限の補償」を担保するのが地震保険の役割です。
地震保険と火災保険の違い
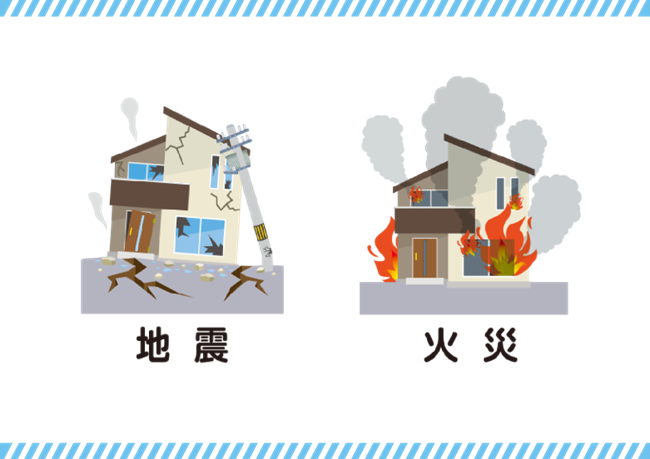
地震保険を正しく理解するためには、まず火災保険との違いを知っておく必要があります。まず押さえておきたいのは、地震保険は火災保険とセットでしか契約できないということ。そして、火災保険は、火事や落雷、風水害などによる損害を補償してくれますが、「地震が原因で発生した損害」は補償の対象外であるという点です。
例えば次のようなケースでは、火災保険だけではカバーできません。
- 地震で建物が倒壊した
- 地震が原因で火災が発生し、住宅が焼失した
- 地震による津波で家財が流された
こうした場合に補償してくれるのが、火災保険とセットで契約する「地震保険」です。地震リスクの大きい日本において、火災保険と地震保険は「車の両輪」のように考えるべきだと言えるでしょう。
地震保険料の仕組みを理解する

地震保険料は、誰でも同じ金額というわけではありません。主に次の三つの要素によって決まります。
建物の所在地
地震リスクが高い地域、たとえば東北地方や関東地方の太平洋側は保険料が高く設定されます。逆に地震リスクが比較的低い地域では安くなります。
建物の構造
木造住宅は地震の揺れに弱いため保険料が高めに設定され、鉄筋コンクリート造の住宅は耐震性が高いとされ、保険料は抑えられる傾向にあります。
保険金額
火災保険の保険金額の30~50%の範囲で設定でき、金額が大きければその分保険料も上がります。例えば建物評価額が3,000万円の場合、地震保険では900万円から1,500万円までを上限に補償を設定できる、という仕組みです。
つまり、地震保険は「地域リスク × 建物の耐震性 × 補償額」で金額が決まる仕組みなのです。
割引制度を賢く活用する

地震保険には、住宅の耐震性に応じた割引制度があります。耐震性が高いほど割引率も大きく、長期的に見れば数十万円単位の節約につながります。これを知っているかどうかで、長期的な負担が大きく変わりますので、住宅選びの際には注目したいポイントです。
以下に代表的な割引制度をまとめます。
| 割引の種類 | 割引率 | 条件・対象 |
| 耐震診断割引 | 10% | 公的機関などによる耐震診断で基準を満たした住宅 |
| 免震建築物割引 | 50% | 免震構造を有する住宅(揺れを建物に伝わりにくくする構造) |
| 耐震等級割引(等級1) | 10% | 住宅性能表示制度で「耐震等級1」と認定された住宅 |
| 耐震等級割引(等級2) | 30% | 同じく「耐震等級2」と認定された住宅 |
| 耐震等級割引(等級3) | 50% | 最も高い「耐震等級3」と認定された住宅 |
| 新耐震基準割引 | 10% | 昭和56年6月以降に建築確認を受けた住宅 |
例えば、東京都内の木造住宅(評価額3,000万円)の場合、割引なしだと年間25,000円かかりますが、耐震等級3を取得すれば半額の12,500円に。こうした差は長期的に見れば非常に大きな節約になります。
また、割引制度を利用するには、必ず「確認書類」の提出が必要です。例えば、耐震等級3の住宅であっても、そのことを証明する「住宅性能評価書」などの公的な書類を保険会社に提出しなければ割引は受けられません。大切なのは「実際に性能があること」だけではなく、「それを証明できる書類があること」です。これを知らずに申込してしまうと、本来受けられるはずの割引を逃してしまう可能性がありますので、事前に住宅会社に確認をしましょう。
耐震等級3を取得していれば地震保険は不要?

ここでよくある疑問が「最高ランクの耐震等級3の住宅なら、地震保険は必要ないのでは?」というものです。確かに耐震等級3の住宅は揺れに強く、倒壊リスクは大幅に減ります。しかし、それだけで完全に安心とは言い切れません。その理由は大きく2つあります。ひとつ目は「揺れ以外の被害」です。地震が原因で起こる火災や津波、噴火による損害は、耐震等級の高さに関係なく住宅や家財を直撃します。地震が原因による火災に対しては、火災保険がおりないため、大きな打撃になります。ふたつ目は「地震の累積ダメージ」について考えなければなりません。建物は一度の大地震だけでなく、中小規模の地震によって少しずつダメージを受けていきます。築年数が経つにつれて耐震性能が低下することもあるため、長期間の安心を保証するわけではありません。したがって、耐震等級3を取得していても地震保険を不要と言い切ることはできません。むしろ、強い建物+保険の補償という二重の備えこそが日々の生活の安心につながります。
火災保険や地震保険は、いつまでに決めておくべきか?

住宅購入や建築の際、火災保険や地震保険は 住宅の引き渡し日までに契約を済ませておくのが基本 です。特に住宅ローンを利用する場合、多くの金融機関で火災保険の加入が「融資の必須条件」とされています。そのため、ローン契約の手続きが完了する前後には保険内容を決定しておくことが望ましいでしょう。また、地震保険は火災保険に付帯する形で加入するため、火災保険を検討する段階で一緒に考えておくことが大切です。特に注文住宅を建てる場合、仕様の決定や打ち合わせに時間を取られてしまい、気づけば建物完成まで日が迫り、保険選びに十分な時間をかけられなかった…という失敗談も少なくありません。後悔しないためにも、早めに検討を始めることをおすすめします。
まとめ
地震保険は1966年に誕生し、国と民間が共同で運営している制度です。その目的は、大地震による経済的な打撃を和らげ、生活再建を支えることにあります。保険料は地域や構造、補償額によって変わりますが、割引制度をうまく活用すれば負担を減らすことができます。また、たとえ耐震等級3の住宅であっても、揺れ以外の被害や累積ダメージを考えれば、地震保険の必要性は変わりません。住宅購入という人生の大きな選択のタイミングだからこそ、火災保険とあわせて「地震保険」をしっかり検討しましょう。忘れてはいけないのが、保険を検討するタイミングです。住宅の引き渡し前に余裕を持って準備し、火災保険とセットで最適なプランを選ぶことが、安心して暮らすための第一歩です。ぜひ、計画的に家づくりを進めてください。