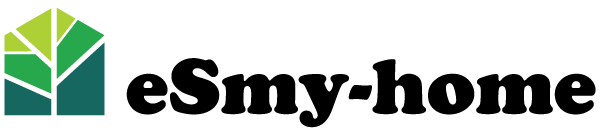
日本に暮らす私たちは、日常生活の中で「地震」という自然災害を避けて通ることができません。
近年も各地で大きな地震が発生し、住宅の被害や生活の混乱が報じられるたびに「自分の家は大丈夫だろうか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。大切な家族を守る「住まい」は、安心して暮らすための拠点です。その住まいが地震の揺れに耐えられるかどうかは、家づくりにおいて欠かせないテーマのひとつといえます。
ここで注目されているのが 「耐震」「免震」「制震」 という3つの仕組みです。どれも“地震に強い家”を実現するために重要ですが、それぞれ役割や考え方は異なります。
本コラムでは、この3つの違いを分かりやすく解説し、「本当に安心できる家づくり」とは何かを考えていきます。
日本と地震の関係

まず押さえておきたいのは、日本が「地震大国」と呼ばれるほど、世界的にも地震の発生が多い国であるという事実です。実際に、世界で発生するマグニチュード6以上の地震のおよそ2割が日本周辺で起きているとも言われています。阪神淡路大震災(1995年)、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)など、過去の大きな地震では住宅の倒壊や損傷が広く報じられ、多くの方が「住まいの安全性」について改めて考えるきっかけとなりました。
日本の建築基準法は、こうした教訓を受けて改正を重ね、現在では「震度6強から7の地震でも1度は倒壊・崩壊しないこと」を目指した最低限の基準が設けられています。
しかし、これはあくまで「1度の地震に対して倒壊しない」ことを目的とした最低ラインに過ぎません。新たな新居に何年住むのか?その間に、何度地震に遭遇するのか?室内の家具が倒れたり、建物が繰り返しの揺れでダメージを受けたりする可能性は残っています。
だからこそ、より安心して暮らすためには、この最低基準を上回る性能を備えた家づくりが求められています。
耐震構造とは?建物そのものを強くする仕組み

耐震(たいしん)とは、建物の強度を強く頑丈にして「地震の揺れに耐える」仕組みのことです。地震に強い家を建てる際に、最も基本となる性能であり、主に地震のエネルギーが直接建物に伝わっても倒れないように、以下のような方法で建物を固く強くつくります。
- 柱や梁を太くする
- 壁の配置を工夫する
- 接合部や金物をしっかり補強する
メリット
- 「倒壊を防ぐ」基本性能として信頼性が高い
デメリット
- 揺れ自体は建物にそのまま伝わるため、家具の転倒や室内被害は避けにくい
- 大きな揺れが繰り返されると、建物へのダメージが蓄積しやすい
耐震はすべての住宅に必須の性能であり、家づくりの出発点といえます。本コラムでは詳細の説明は控えますが、耐震性能はどんな計算方法でどの耐震等級を取得しているのかが大切なキーポイントとなります。ご興味のある方は、下記のコラムをご覧ください。

免震構造とは?揺れを建物に伝えない仕組み

免震(めんしん)とは、「地震の揺れを建物に直接伝えず、逃がす」構造です。建物と基礎の間に「免震装置」と呼ばれる特殊なゴムや金属部材を設置し、揺れを吸収・分散することで、建物自体に直接伝わらないように、揺れを小さくします。イメージとしては、建物が基礎の上に“浮いている”ような状態です。
メリット
- 建物全体の揺れを大幅に減らすことができ、家具や家電の転倒リスクを抑えられる
- 建物自体の損傷も軽減されるため、地震後も安心して暮らしやすい
デメリット
- 導入コストが高く、一般住宅での普及はまだ限定的
- 設置できる地盤条件に制限がある場合がある
免震は「揺れそのものを避ける」という理想的な仕組みですが、価格等といった条件面から、一般住宅での採用は少なく、主に公共施設や高層ビル等で採用されている傾向にあります。
制震構造とは?揺れを吸収してダメージを減らす仕組み

制震(せいしん)とは、建物に伝わった揺れを吸収して「建物のダメージを減らす」仕組みです。自動車のショックアブソーバーのように、地震のエネルギーを摩擦や粘りで熱に変換し、建物全体の揺れをやわらげます。具体的には、柱や壁の内部に「制震ダンパー」と呼ばれる装置を組み込み、地震が起きるたびにエネルギーを吸収する仕組みです。
メリット
- 繰り返す余震にも効果を発揮し、建物の寿命を守る
- 耐震だけの場合よりも揺れを小さく抑えられる
- 免震に比べるとコストを抑えやすく、一般住宅にも導入しやすい
デメリット
- 揺れをゼロにはできない
- 耐震だけの住宅よりは建築費用が増える
制震は「家を倒れにくくする」だけでなく「家を長持ちさせる」仕組みとして注目されています。
過去の大地震で分かった実績データ

過去の大地震により、耐震性能の見直しが行なわれてきました。そのたびに、性能基準だけではなく、家を選ぶオーナー様の耐震基準への見方が変わり、住宅購入時に選択する耐震等級を大切にするご家族が増えていきました。
阪神淡路大震災(1995年)
マグニチュード7.3、最大震度7を記録した阪神淡路大震災では、約24万棟の住宅が全壊しました。当時は古い耐震基準の住宅が多く、耐震性能が不足していた建物が大きな被害を受けたことが明らかになりました。一方で、新耐震基準(1981年改正以降)に基づいて建てられた住宅は倒壊が少なく、基準の重要性が広く認識されるきっかけとなった大地震でもあります。
東日本大震災(2011年)
マグニチュード9.0という観測史上最大の地震となった東日本大震災。津波の被害が大きく報じられましたが、内陸部の建物被害では免震や制震の効果が注目されました。実際に、免震構造のマンションや公共施設では建物の揺れが大幅に抑えられ、エレベーターや室内設備の被害が軽微だったという報告がありました。また、制震装置を導入したビルでは、繰り返す余震に耐え、継続利用が可能だった例も見られたそうです。
熊本地震(2016年)
熊本地震は、短期間に震度7の地震が2度発生するという特殊なケースでした。耐震性が不足していた木造住宅は大きな被害を受けましたが、取得していた家や制震ダンパーを備えた住宅では損傷が軽く済んだとの報告があります。繰り返す大きな揺れに対して制震性能が有効であることが実証され、この地震をきっかけに戸建て住宅でも制震技術を導入する動きが一層広がりました。一方で、住宅性能表示制度による耐震等級3の住宅は大きな損傷が見られず、大部分が無被害であったという報告があり、耐震性能の高さが今後の住まいの倒壊防止の鍵であると言われています。
実績から見えてくる「優先順位」と選び方

過去の大地震の教訓から学べることは、「まず耐震性能を確保することが最優先」という点です。地震の揺れを抑える制震装置や、揺れそのものを建物に伝えにくくする免震装置は確かに有効ですが、それらはあくまで“プラスアルファの補助”であり、基盤となる耐震性能がしっかりしていなければ効果を発揮できません。
- 耐震等級の確保が第一
建築基準法の最低基準(耐震等級1)では、長く安心して暮らすには十分とはいえません。住宅性能表示制度で最も高い「耐震等級3」、あるいは許容応力度計算によって導き出された等級2以上を取得することが望ましいといえます。これが「地震に強い家」の出発点です。 - 制震装置はあくまで補助
制震装置をつければ安心、というわけではありません。構造体としての安全性を確保したうえで、その性能を長持ちさせるために制震装置を組み合わせる──これが正しい順序です。建物の設計によっては制震装置の配置がうまく機能しない場合もあり、数十万〜数百万円の投資に見合う効果を得られないこともあります。 - 免震は現実的には限定的
免震は大地震時に非常に効果的ですが、コストが高く敷地条件も限られるため、一般の戸建て住宅ではまだまだ現実的ではありません。病院や大規模マンションなど、特別な用途の建物に適した技術といえるでしょう。
つまり「どれかひとつが万能」というわけではなく、それぞれに役割と強みがあります。大切なのは、「地震に強い家=耐震性能を高めた家」であることを前提に、生活スタイルや予算、地域特性に応じて制震や免震を検討すること なのです。
まとめ
災害に強い家を考えるとき、まず大切にすべきなのは「耐震性能の確保」です。制震や免震は確かに有効な技術ですが、それらはあくまで耐震を前提としたプラスアルファの選択肢となります。最近では、地震対策を重視される方が増えているため、制震装置を標準仕様としてアピールする会社もありますが、「制震装置が付いている=地震に強い家」というわけではありませんので注意が必要です。基本となる耐震性能がしっかり確保されてこそ、制震や免震の効果が発揮されます。
私たち eSmy-home株式会社 では、許容応力度計算による耐震等級3の家づくりをご提案しております。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。









