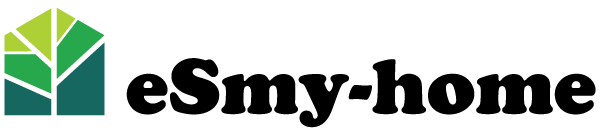
家を建てるとき、誰もが「長く安心して暮らせる家にしたい」と思いますよね。しかし現実には、日本の住宅の平均寿命は約30年ほどと言われています。欧米諸国と比べて短く、建て替えのサイクルが早いといわれています。
そんな中、「長く使い続けられる家づくり」を国が後押しする仕組みとして登場したのが『長期優良住宅』という制度です。
この制度は、“長く・快適に・安心して住める良質な住宅”を増やすことを目的に2009年に始まりました。
「長期優良住宅」という言葉を聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実は家族が安心して住める良い家の証でもあります。本記事では、長期優良住宅とは、どういう制度なのか?制度を受けるとどんなメリットがあるのか?注文住宅を検討している人はどんな点に注意をするべきなのか?という点について、分かりやすくご紹介をして参ります。
「長期優良住宅」とはどんな家?

長期優良住宅とは、「つくっては壊す」という日本の住宅文化から脱却し、“良いものをつくって、きちんと手入れをして、長く大切に使う”という考え方をもとに生まれた国の住宅制度です。この理念に基づき、国が定める住宅性能基準を満たした住宅が、自治体から「長期優良住宅」として認定を受けることができます。つまり、長期優良住宅とは「長く良好な状態で済み続けられるための措置を講じた性能の高い住宅」であると、国から品質を認められた住宅であるということを証明をする制度と言えます。
認定されるための主な基準

長期優良住宅の認定を受けるためには、指定された住宅性能基準を満たす必要があります。どの基準も長く住み続けるために欠かせない性能に関わる重要なポイントとなっております。以下では、主な認定性能項目ごとに制度上の基準のポイントとを整理します。
1. 劣化対策(構造躯体を長く維持するための措置)
構造躯体が数世代(おおよそ100年程度)にわたって良好に使用できるよう、適切な措置を講じることが求められています。 具体的には、住宅性能表示制度における「劣化対策等級3」に適合し、さらに木造なら床下や小屋裏の点検口を設置し、床下空間の有効高さ確保(例330mm以上)などの措置が必要です。
2. 耐震性(地震等自然災害への備え)
極めて稀に発生する大地震に対しても「継続使用を可能とするための改修の容易性」を図るため、損傷レベルを低く抑える措置が必要である。新築住宅であれば、「耐震等級(倒壊等防止)等級2」以上、あるいは「耐震等級1+一定の変形制限」などの選択肢が提示されています。
3. 省エネルギー性(断熱・気密・エネルギー効率)
必要な断熱性能・気密性能・一次エネルギー消費量削減性能などが確保されていることが基準となります。「断熱等級5」以上や「一次エネルギー消費量等級6」以上など、地域・仕様に応じた等級適合が要件となります。
4. 維持管理・更新の容易性(設備・内装・配管などの将来性)
構造躯体に比べて耐用年数の短い設備・内装・配管などについて、点検・補修・交換が容易に行える設計措置が必要です。 宅性能表示制度における「維持管理対策等級3」を満たしていることなどが適用要件とされます。
5. 可変性(ライフスタイル変化に対応できる住宅設計)
戸建て住宅は対象外となりますが、主に共同住宅や長屋を建築する際には、その躯体天井高さは2,650mm以上と定められています。
6. バリアフリー性(高齢になっても住み続けられる配慮)
こちらも、一般戸建て住宅では対象外です。主に共同住宅等の共用部分について将来のバリアフリー改修を見据えた措置(共用廊下・階段・出入口等に必要なスペース確保)などが要件となっており、「高齢者等配慮配慮対策等級3」以上を満たしている必要があります。
7. 居住環境(まちなみ・敷地・周辺環境との調和)
住宅が建つ地域の景観、住環境(騒音・日照・通風など)に配慮がされており、街並みに調和する設計であることが要件となっています。
8. 住戸面積(良好な居住水準を確保)
良好な居住水準を確保するため、住戸の専有面積・1階の床面積等に最低基準が設けられています。戸建て住宅であれば75㎡以上、共同住宅55㎡以上など。地域・自治体により若干の調整はございますが、コンパクトな住まいづくりを希望されている方は特に、最低床面積についても把握しておく必要があります。
9. 維持保全計画(将来にわたる点検・修繕・更新の計画)
建築時点で「維持保全するための計画を策定し、その通りに点検をしましょう」と定められています。主に構造耐力上主要な部分や雨水浸入防止部分、給排水設備などについて点検時期・内容が明記されている必要があり、少なくとも10年ごとに点検を行うことが求められています。 この基準は、建築後の長期にわたる住宅維持管理をしていくための大切な要件です。
10.災害配慮(建築地の災害ハザードマップをチェック)
最近の改正によって、災害配慮(洪水・高潮・土砂災害の想定区域における配慮)も認定基準に盛り込まれました。これによって、災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じることが求められるようになりました。特に、「土砂災害危険区域」にある土地を購入する際は、長期優良住宅の認定を受けることができない土地のため、注意が必要です。
認定を受けるとどんなメリットがあるの?

1. 税制優遇 ─ 家を建てた後の税負担が軽くなる
長期優良住宅に認定されると、さまざまな税金が通常より優遇されます。
家を建てている時や購入後、所有している間の税金が軽減されるため、トータルで数十万円~数百万円の違いになることもあります。
(1)住宅ローン控除の優遇
住宅ローンを利用して家を建てた場合、所得税や住民税の一部が控除される「住宅ローン控除」が適用されます。長期優良住宅では、一般住宅よりも控除額の限度額の引き上げがあるのが特徴です。
| 区分 | 長期優良住宅以外の住宅 | 長期優良住宅 |
|---|---|---|
控除限度額 | ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 (子育て世帯 4,500万円) 省エネ基準適合住宅 3,000万円 (子育て世帯 4,000万円) その他の住宅 0円 | 一般家庭 4,500万円 (子育て世帯 5,000万円) |
※ 政策の年度によって変動があるため、詳しくは最新の国税庁情報をご確認ください。
(2)登録免許税の軽減
家を建てたあと、不動産登記を行う際にかかる「登録免許税」が軽減されます。 登録免許税は建物価格に対して課税されるため、数十万円規模の差になることもあります。
| 区分 | 一般住宅 | 長期優良住宅 |
|---|---|---|
| 登録免許税(保存登記) | 0.15% | 0.1%に軽減 |
(3)固定資産税の減額期間が延長される
新築住宅には、完成後の3年間、固定資産税が半額になる特例があります。長期優良住宅の場合は、この期間が5年間に延長されます。 2年分の延長は、平均すると十数万円~数十万円の節税効果になります。
| 区分 | 一般住宅 | 長期優良住宅 |
|---|---|---|
| 固定資産税の減額期間 | 3年間 | 5年間(2年延長) |
(4)不動産取得税の軽減措置も拡充
新築時に一度だけかかる「不動産取得税」についても、長期優良住宅は控除額が大きくなります。より高性能な住宅ほど、税制上も優遇される仕組みになっています。
| 区分 | 一般住宅 | 長期優良住宅 |
|---|---|---|
| 控除額 | 1,200万円 | 1,300万 |
2. ローン金利の優遇 ─ フラット35Sなどで金利が下がる
住宅金融支援機構が運営する【フラット35】(長期固定金利型住宅ローン)では、長期優良住宅が「フラット35S」の対象となり、一定期間金利が優遇されます。
| 区分 | 一般住宅 | 長期優良住宅(フラット35S) |
|---|---|---|
| 金利引下げ幅 | ― | 当初5~10年間、金利-0.25% |
注文住宅で「長期優良住宅」を建てる際の注意点

注文住宅で長期優良住宅の認定を受けたい場合、主に3つの点に注意が必要です。
● 認定が下りるまで工事は始められない
この認定申請の最大の注意点は、一般住宅よりも工期が長くなる点にあります。通常の建築確認申請に加え、長期優良住宅の申請を行う必要があり、通常の申請時よりも約1か月程おおく審査日程がかかります。また、当然ではございますが、認定が正式に下りる前には工事(着工)を始めることはできません。そのため、建物の完成予定スケジュールを後ろ倒しにすることが困難な方には、少しハードルが高いとも言えます。不測の事態にも安心して対応できるよう、余裕をもったスケジュールを立てる必要があります。
● 設計は最初から「長期優良住宅仕様」で進める
長期優良住宅の審査は、完成後の家ではなく、設計図の段階で行われるのが特徴です。つまり、「建てたあとで認定を取る」ということは原則難しいと言われています。そのため、家の設計を依頼するときには、「長期優良住宅として認定を取りたい」と最初に伝えておくことがとても大切です。途中で性能を変えたり、間取りを変更したりすると、基準を満たせなくなり再申請が必要になることもございますのでご注意ください。
● 申請には追加費用がかかる
長期優良住宅の申請には、設計者による書類作成や行政への審査手数料が必要です。
一般的な目安としては、
- 申請書類の作成・性能計算など:10〜20万円前後
- 行政への審査手数料:数万円程度
合計で10〜30万円ほどの費用がかかります。
一見高く感じるかもしれませんが、その後に受けられる税金の優遇(住宅ローン控除・固定資産税減額など)を考えれば、十分に元が取れる金額です。
まとめ
長期優良住宅は、長く安心して暮らせる家として国が認める制度です。耐久性や耐震性、省エネ性能、将来のメンテナンスのしやすさなど、暮らしを長期的に支えるための基準を満たすことで認定を受けられます。
設計段階からの対応が必要であること、認定が下りるまで着工できないこと、申請に一定の費用がかかることには注意が必要ですが、
その分、税制優遇や住宅ローンの金利優遇といった大きなメリットを受けられます。
これから家づくりを考える方にとって、長期優良住宅は“将来にわたって資産価値を守る選択肢”の一つと言えるでしょう。ぜひ、安心で快適な住まいを目指す第一歩として、長期優良住宅の認定を受けた家づくりをご検討ください。









