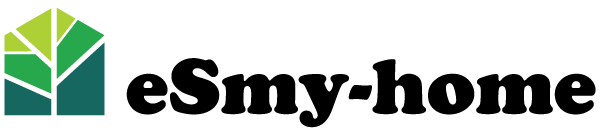
家づくりを進めると、見積書や設計図面、建築確認申請などで「延べ床面積」という言葉が必ず登場します。さらに、ハウスメーカーや工務店の資料には「施工床面積」という表現も出てきます。
一見すると似ている言葉ですが、実は使われる場面や意味する範囲が大きく違います。そのため、「どっちの数字を見ればいいの?」「延べ床面積が少ないのに施工床面積が大きいのはなぜ?」といった疑問が多く寄せられます。
この記事では、延べ床面積と施工床面積の違いを整理し、建築計画を理解するうえで役立つポイントをわかりやすくご紹介いたします。
延べ床面積とは?

延べ床面積(のべゆかめんせき)とは、建築基準法で定められた用語で、建物の各階の「床面積」を合計したもののことです。これは、建築確認申請において必須の数値であり、また建蔽率や容積率の計算や固定資産税の評価など、法律や税金に直結する非常に重要な指標です。もっとイメージがしやすいように簡単にお伝えすると建物の内部空間の人間が歩いて行けるところが延べ床面積に含まれる部分です。注意するべきは、内部空間でも歩くことができない吹抜けや外部空間のバルコニーや玄関、ポーチ等は延べ床面積に含まれない、という点です。
延べ床面積 = 各階の床面積の合計
例)2階建て住宅の場合:
- 1階:50㎡
- 2階:40㎡
➡ 延べ床面積 = 90㎡
施工床面積とは?

一方、施工床面積(せこうゆかめんせき)は法律用語ではなく、工務店やハウスメーカーが建築費を算出するために使う各会社の独自の基準によって算出される面積です。一般的に、施工床面積には、延べ床面積には含まれていないが実際に施工工事をしている部分まで含めて計算されることが多いのが特徴です。
施工床面積に含まれる例
- 延べ床面積に含まれる室内空間
- バルコニー(屋根の有無に関わらず)
- ロフト(高さが1.4m以下でも施工上は工事対象なので計上されることが多い)
- 吹き抜け周辺の施工部分(足場や仕上げのための工事が発生するため)
- 玄関ポーチや外部階段
つまり、「施工にかかる工事範囲の床面積」を示しており、多くが工事費用や坪単価の算出に使われています。
延べ床面積と施工床面積の違い

整理すると以下のようになります。
| 項目 | 延べ床面積 | 施工床面積 |
| 定義 | 建築基準法で定められた床面積の合計 | 工事費を算出するための施工範囲の床面積 |
| 主な用途 | 建築確認申請、容積率計算、固定資産税 | 見積もり、坪単価の算出 |
| 含まれる範囲 | 各階の居室など | 延べ床面積+バルコニー、ロフト、ポーチなど |
| 施主への影響 | 法律上の制限や税金に直結 | 建築費に直結 |
なぜ違いがあるのか?

多くの施主が「なぜ2種類の面積があるの?」と疑問に思うのは当然です。理由は 「延べ床面積は法律上の数値」「施工床面積は工事の実態を表す数値」 だからです。
例1:バルコニー
- 建築基準法上
→ 屋根がなければ延べ床面積に含まれない。 - 工事上
→ 床材・防水・手すり・仕上げが必要なので 施工床面積に含まれる。
例2:吹き抜け
- 建築基準法上
→ 床がないため延べ床面積には算入されない。 - 工事上
→ 吹き抜け周囲の壁や手すり、仕上げ工事は必要なので施工床面積に影響する。
例3:ロフト
- 建築基準法上
→ 高さ1.4m以下なら延べ床面積に含まれない。 - 工事上
→ 床や仕上げを造作するので施工床面積に含めるケースが多い。
つまり、法律でカウントされない部分でも、実際には工事費がかかるため施工床面積には反映される、というのが両者の違いです。
施主が注意すべきポイント
- 建築確認申請や法規制を確認するなら延べ床面積
- 建物の価格や坪単価を比較するなら施工床面積
この2つは使われる場面がまったく異なるため、混同しないことが大切です。
さらに、ハウスメーカーや工務店によって「施工床面積」の定義が微妙に異なることもあります。契約前に「どの範囲を施工床面積に含めているのか」を必ず確認しておきましょう。
まとめ
家づくりにおいて「延べ床面積」と「施工床面積」はよく似た言葉ですが、その役割は大きく異なります。延べ床面積は建築基準法に基づいて定義される数値で、建築確認申請や容積率の計算、さらには固定資産税の評価といった、法律や税金に関わる重要な指標です。一方で施工床面積は、実際に工務店やハウスメーカーが工事を行う際の施工範囲を表しており、見積もりや坪単価の算出に使われます。そのため、延べ床面積には含まれないバルコニーやロフト、玄関ポーチなども、施工床面積には計上されることが多いのです。
そのため、これから家づくりを検討される方にとって大切なのは、両方の数字を混同せずに用途ごとに確認することです。それが、後々の住宅会社との認識の違いといったトラブルを避けることへ繋がります。









