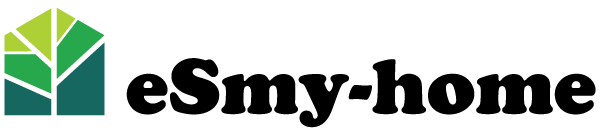
マイホームを購入するというのは、多くの人にとって人生最大の買い物です。間取りやデザイン、立地などに気を取られがちですが、実はそれと同じくらい大切なのが「住宅の品質」や「万が一の備え」です。
「もし家に欠陥があったら?」
そんな“もしものとき”に、住宅購入者を守ってくれるのが 住宅瑕疵(かし)担保責任保険(住宅瑕疵保険)、通称「住宅瑕疵保険」です。
この記事では、これから住宅を購入する方に向けて、住宅瑕疵保険の基本的な仕組みと、2025年10月1日に新たに登場した 「20年瑕疵保険」制度 について分かりやすくご紹介して参ります。
「住宅瑕疵保険」とは?

住宅瑕疵保険の「瑕疵(かし)」とは、建物の構造や防水などに関する「欠陥」や「不具合」を指します。つまり、本来あるべき住宅性能や品質を守れていない状態にあることを意味します。たとえば、住み始めて数年で雨漏りが発生した、基礎部分にひび割れが見つかった、柱が傾いた――。
こうしたトラブルは必ずしも経年劣化が原因とは限らず、工事中のミスが原因によって発生してしまったという事例もあります。
そのため、住宅の建築業者には引渡し後に欠陥が見つかった場合、一定期間その修繕責任を負う「瑕疵担保責任」があります。
この責任を確実に果たせるよう、国の法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づき導入されたのが「住宅瑕疵保険」です。
保険の仕組みと対象範囲

(1)保険に加入するのは「建てる側」
住宅瑕疵保険に加入するのは、住宅を建てる工務店やハウスメーカーなどの事業者です。事業者が保険法人と契約し、その住宅が基準を満たしているかを施工段階で第三者機関が検査します。これにより、施工中から品質のチェックが行われ、欠陥を未然に防ぐ役割も果たしています。
(2)もし欠陥が見つかったら?
引渡し後に欠陥(瑕疵)が判明した場合は、まず施工会社が補修対応を行います。その際に、かかった費用は瑕疵保険によってカバーされます。万が一、施工会社が倒産してしまっていた場合でも、その補修にかかった費用を住宅購入者が直接、保険法人へ請求し、保険法人が直接住宅取得者に保険金を支払う仕組みとなっています。
(3)対象となる部分
瑕疵保険の対象は、住宅の中でも特に重要な部分です。
- 構造耐力上主要な部分(基礎・柱・梁・床・屋根など)
- 雨水の浸入を防ぐ部分(屋根・外壁・開口部など)
これらは住宅の「骨格」と「防水性能」に関わる部分で、家の安全と耐久性を守る上で欠かせない「家の安全性」と「雨漏りを防ぐ部分」が保険の範囲となっています。一方で、キッチンやトイレなどの設備・内装部分は瑕疵保険の対象外となる場合が多い点に注意が必要です。瑕疵保険に含まれていない場合は、他の保証でカバーされているかチェックしましょう。
保証期間と基本ルール

従来、住宅瑕疵保険の保証期間は「引渡しから10年間」が基本でした。この10年という期間は、住宅の構造や防水に関する瑕疵担保責任を事業者に課す法律(品確法)に基づいています。つまり、これまでの新築住宅では、「10年間は保険と法律で守られる」というのが一般的な仕組みでした。
10年間でも安心できますが、その後の期間については事業者独自の保証や、点検を条件とした延長保証などに頼るケースがほとんどで、制度としての“長期保証”は存在していませんでした。
その状況が今年の10月1日に大きく変わりました。
新たに始まった「20年瑕疵保険」制度とは?

2025年10月1日から、これまでの10年保証に代わる新たな制度として、「20年瑕疵保険」が正式にスタートしました。
(1)制度の概要
新築住宅の引渡し時点で、最長20年間の保険期間を一括して契約できる制度です。これにより、途中で延長手続きや追加費用を支払うことなく、20年間の長期保証を受けられるようになりました。加入できるのは、構造や防水性能において一定の耐久性基準を満たした住宅に限られています。
(2)これまでの「延長保証」との違い
これまでの延長保証制度は、10年経過時に点検・修繕を行うことで「+10年延長」という形式でした。一方、新しい20年瑕疵保険は、引渡し時に20年間分の保険契約が成立するという点が大きく異なります。つまり、「10年経過時に再契約の手間が不要」で「最初から20年の安心を得られる」という仕組みです。
(3)制度誕生の背景
日本では住宅の平均寿命が30年以上に延び、「10年保証では短すぎる」という声が多く聞かれていました。加えて、地震・台風・豪雨など自然災害の頻発により、住宅の耐久性や防水性能への不安が高まっていたことも影響しています。こうした中で、国土交通省の方針や業界の動きを受け、保険法人・住宅事業者が連携して制度を刷新するに至りました。長く安心して住める住宅を社会全体で支えるための仕組みとして、この20年瑕疵保険が誕生したのです。
購入者にとってのメリット

(1)引渡し時から20年間の安心
引渡しの瞬間から、構造・防水部分に関する不具合が20年間補償されるため、長期的な安心が得られます。加えて、以前のような途中で保険切れや更新手続きをしなければいけない、といった煩わしさがなく、アフターメンテナンスの充実性を求める方には、嬉しい部分ではないでしょうか。特に家を長く所有する予定の方には大きなメリットと言えます。
(2)将来の修繕コストを抑えやすい
住宅の不具合は10年を過ぎてから発生するケースも多いため、20年間の補償があることで、突発的な修繕費用のリスクを軽減できます。昨今では、住宅資材の高騰により住宅購入費用が高くなっていることもあり、住み始めてからの突発的な支出を避けたいと考えている方には安心できる要素の一つだと言えます。
(3)保険法人の裏付けがある安心の仕組み
この保険は、保障を“ただ住宅会社の仕様保証”という形に留めず、保険法人が引き受ける「瑕疵保険」の枠組みを使っており、施工会社が万が一倒産した場合でも保険法人に請求できるなど、購入者保護の観点も配慮されています。
加えて、保証期間の長い住宅は、将来的に売却や相続の際にもプラス評価となります。こうした資産運用の観点からも「長期保証付きの住宅」は価値が高いといえます。
契約前に確認しておきたいポイント

始まったばかりの新制度のため、新制度を利用したいとお考えの方は、住宅会社を選ぶ際に以下の点をしっかりと確認することが大切です。
- 20年瑕疵保険に正式対応しているか
すべての住宅会社が対応しているわけではありません。保険法人と提携しているか必ず確認をしてください。 - 保証の対象範囲
構造・防水部分が主な対象で、設備や内装は別保証になる場合があります。その場合は、設備保証についても、どのような保証があるのか必ず確認しましょう。
- 対象住宅の基準
長期耐久仕様や一定の施工基準を満たす住宅のみが対象となることがあります。住宅会社から提案を受けている住宅性能で、保証が問題なく付与されるかについても質問してみましょう。
まとめ
住宅瑕疵保険は、見えない部分のリスクから住まいと家族を守る大切な制度です。そして、2025年10月に始まった20年瑕疵保険は、これまでの「10年保証」の常識を大きく変える新しい仕組みとなりました。長く利用する家だからこそ、これから家を購入する方は、デザインや価格だけでなく、「どんな保険・保証で守られている住宅か」 という視点を持って住宅を選ばれてはいかがでしょうか。安心して長く暮らせる住まいを選ぶために、ぜひ新しい20年瑕疵保険制度にも注目してみてください。









