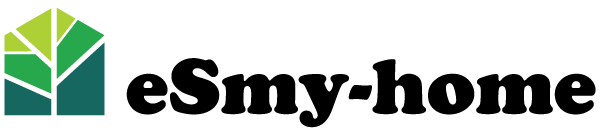
「家って何年くらい住めるんだろう?」
住宅を購入しようと考えたとき、気になるのが「耐用年数」です。「家は築30年で価値がなくなる」と聞いたことはありませんか?新築物件や注文住宅だけではなく、中古住宅を検討している人は特に「築30年以上だと住宅ローンが通りにくい」「価値がないと言われた」といった話しを聞いたことがあるかもしれません。これらの考えの根拠には「法定耐用年数」という、国税庁が定める税務上の基準が大きく関わっています。しかし、この数字は、あくまで減価償却のための数値であり、 “住める年数”とはイコールではないことをご存じでしょうか?
本日のコラムでは、戸建ての寿命と注文住宅を選択をする購入者の「住まい」の価値観についてご紹介いたします。
法定耐用年数とは? 〜「税務上の寿命」にすぎない〜

「法定耐用年数」とは、簡単に言えば税務処理のために国が決めた“建物の資産の寿命”です。企業が所有する資産は、時間の経過とともに価値が減っていきます。その減少分を経費として計上する「減価償却」のために使われる基準が、法定耐用年数です。
■ 主な建物の法定耐用年数一覧
| 構造 | 法定耐用年数(税法上) |
| 木造住宅 | 22年 |
| 軽量鉄骨造(厚さ3mm未満) | 19年 |
| 鉄筋コンクリート(RC) | 47年 |
| 鉄骨造(厚さ4mm超) | 34年 |
ポイントは、この年数が税金計算上のルールでしかないということです。たとえば木造住宅の22年という数値も、「22年経ったら住めない」という意味ではありません。
実際の住める年数は? 〜適切な手入れで50年以上使える〜

法定耐用年数を超えた住宅が、すぐに取り壊されているかといえば、そうではありません。日本全国には築50年以上の住宅が数多く存在し、今も人が普通に暮らしています。メンテナンスやリフォーム、耐震補強によって実際の寿命は50年〜70年に延びる事例も多数あります。そして、近年では中古住宅+リノベの流行により、築古物件への価値再評価が進んでいます。
■ 実際の寿命に影響する3つの要素
- 構造と施工の質
RC造や鉄骨造はもちろん、木造住宅でも耐震基準を満たし、構造がしっかりしていれば50年〜60年持つ例も珍しくありません。 - メンテナンス履歴
外壁塗装、防水工事、配管の更新など、適切なタイミングで手を入れていれば、家の劣化は大幅に抑えられます。 - リフォーム・リノベーション
近年は、古い家を再生する「リノベ住宅」も人気。設備を入れ替え、間取りを一新すれば、古さはむしろ“味”になります。
築年数=寿命 ではない!
建物の寿命は“使い方”と“手入れの頻度”に左右されます
住宅ローンとの関係 〜築年数が融資の可否に影響する理由〜

住宅ローンを組む際、銀行や金融機関がチェックするポイントの一つに「築年数」があります。なぜなら、担保価値を評価する際に、建物の法定耐用年数が目安として使われているからです。
■ 中古住宅とローン審査の関係
- 木造住宅で築25年以上になると、金融機関によっては「担保価値ゼロ」と見なされるケースも
- 法定耐用年数を超えている物件は、ローン返済期間が短縮される可能性あり
- リノベーション済み物件は担保評価が高まる傾向
また、住宅ローン控除を受けるには「築20年以内(木造)」または「耐震基準適合証明」が必要とされます。これを知らずに契約すると、数十万円単位の損失になる可能性も。
銀行では「残価の見込み」を元にローン審査
中古の場合、法定耐用年数の残存期間が審査に影響を与えるケースも
住宅ローン控除(減税)制度には築年数の条件がある場合あり
「負動産」とは? ~マイホームは資産?住まいを残し、受け継ぐ~

「負動産(ふどうさん)」という言葉をご存知でしょうか?これは、固定資産税や修繕費などの維持コストばかりがかかり、売るにも貸すにも困る不動産を指す、近年注目されている言葉です。日本では、人口減少や空き家の増加、都市集中の進行によって、地方を中心に「資産価値の下がった持ち家」が急増しています。
■持ち家が負動産になる4つの要因
- 立地条件が悪く需要がない
- 老朽化が進み、安全性に不安がある
- 適切なメンテナンスがされていない
- 所有者不明や相続放棄による放置状態
これらの家は、相続しても売れず、維持費ばかりがかかる“負の遺産”となりかねないことから、持ち家は「負動産」となる、と言った認識をお持ちの方が少なくありません。しかし、近年の家づくりは住宅寿命や耐久性に重きを置いた家づくりが増えており、昔のような「スクラップアンドビルド」ではなく「ストック活用」に注目が集まっています。
■家を“暮らしの資産”に変えるという考え方
家は単に「売れるかどうか」だけで価値を測るものではありません。むしろ、家族が安心して暮らせる場所、代々住み継いでいける暮らしの拠点としての価値こそ、本来の意味での“資産”ではないでしょうか。
子や孫へ「安心して引き継げる家」をつくるためのポイント
- 計画的なメンテナンス(屋根・外壁・配管など)
- バリアフリー化や耐震補強による安全性の向上
- ライフステージに合わせた間取り変更(リノベーション)
こうした工夫を重ねることで、築年数が経っても“住める・使える・受け継げる家”としての価値が保たれます。
■ リフォーム・リノベーションで「住み継ぐ」ことの価値
将来、子世代が新たに住宅を建てるのではなく、親世代の家をリフォームして住むという選択肢は、実は非常に合理的で、経済的なメリットも大きいです。
| 比較項目 | 新築戸建て購入 | 実家のリノベーション |
| 費用相場 | 3,000〜5,000万円以上 | 500〜2,500万円前後 |
| 所要期間 | 約6ヶ月〜1年 | 約1〜4ヶ月 |
| 維持コスト(初期) | 新築のため低い | 築年数により修繕も必要 |
| 愛着・思い出 | なし(新規) | あり(家族の歴史) |
| 立地(親世代の資産) | 選択肢多いが土地購入が必要 | 土地代不要で経済的 |
親世代がしっかりと家の維持管理をしておけば、次世代は“建てる”より“引き継ぐ”という選択肢を取ることができます。その結果、住宅取得にかかるコストを大幅に削減でき、教育費・旅行・趣味・老後資金など、他の豊かさのためにお金を使えるようになります。
■ 「家=暮らしを豊かにする手段」として考える
「資産になるかどうか」という投資的な視点だけでなく、暮らしを楽しむ場所・家族の時間を育む空間として住宅を捉えることが、これからの時代の家の価値観になりつつあります。
- 休日に庭でバーベキューをする
- 家族でDIYや模様替えを楽しむ
- 子どもや孫が遊びに来る拠点となる
こうした“豊かな時間”こそが、目には見えない「家の価値」をつくります。そして、その価値は引き継がれ、次の世代の生活を支える存在になっていきます。
まとめ
住宅の価値は、「法定耐用年数」や「築年数」といった数値だけでは語りきれません。法定耐用年数はあくまで税務処理上のルールであり、実際の住まいの寿命や価値は、日々のメンテナンスと暮らし方次第で大きく変わります。私たちはつい、「住宅は資産でなければならない」「築年数が価値を決める」といった考えに縛られがちです。しかし本来、住まいは人生を安心して楽しむための場所であり、“家族と時間を共有する器”です。そして、近年話題となっている「負動産」という言葉は、家が“資産”として扱われることの難しさを浮き彫りにしています。老朽化した家をメンテナンスし、未来に引き継いでいくという姿勢は、単なる不動産の延命ではなく、暮らしそのものを大切にする生き方の表れでもあります。
これから家を買う人も、住み替えを考えている人も、すでに家を所有している人も。
「この家をどう活かせば、家族の未来がもっと自由で、もっと豊かになるのか?」
そう考えることが、負動産にしない、家の在り方と言えるのではないでしょうか。









