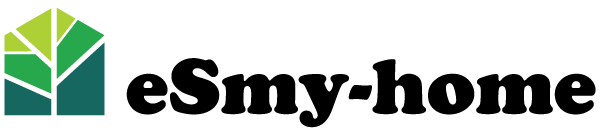
「床」は面積が広く、内装や家全体の雰囲気を決める大きな要素であり、常に肌に触れる部分です。そのため、床選びはとても大切です。近年では、注文住宅を建てる多くの方が天然木を使った無垢フローリングを採用されています。しかし、無垢材にはメリットだけではなく注意点も多く、「思っていたのと違った…」という後悔の声も少なくありません。
本コラムでは、注文住宅で無垢フローリングを採用する際に知っておきたい5つの選び方のポイントを、ご紹介いたします。失敗しない床選びの参考にぜひご活用ください。
無垢フローリングとは?|合板との違いを知る

無垢フローリングとは、一枚の天然木から切り出された100%木材の床材です。木そのものの風合いや質感が楽しめるのが特徴で、時間の経過とともに色味や艶が変化する「経年美化」が魅力のひとつです。
一方、一般的な「複合フローリング」や「合板フローリング」は、薄い木の板を何層にも重ねて接着したものです。見た目は似ていても、足触りや調湿性には大きな差があります。無垢材は調湿効果が高く、室内の湿度を自然に調整してくれるため、快適な住環境づくりにも貢献します。一方で、温湿度の変化に敏感で反り・割れといった現象が起きやすいため、正しい施工や日常管理が求められることを忘れてはいけません。
合板フローリングとの主な違い
- 触感:無垢材は肌触りがやわらかく、素足で歩いた時に心地よさが感じられます。
- 調湿性:空気中の水分を吸放出するため、湿度の変化を和らげ、快適な室内環境に。
- 経年美化:紫外線や時間による色の変化が味わいとなり、住まいと共に“育つ”感覚を味わえます。
木材の種類を知る|用途に合った樹種を選ぼう

無垢フローリングの特徴の一つは、独特の風合いや温かみがあることです。木目や質感が一つ一つ異なり、時間と共に深みを増していく魅力があります。また、経年変化により、色合いや艶が変わることで、長く使うほどに愛着が湧いてくる素材です。しかしながら、無垢フローリングに使われる木材は多種多様です。それぞれに特徴があるため、樹種の特徴を知って選ぶことが大切です。以下に床材に採用される代表的な樹種をご紹介いたします。
✅ オーク(ナラ)
- 特徴:硬くて重厚感があり、耐久性に優れる。
- 色味:明るめのナチュラルブラウン。
- おすすめ用途:リビング・ダイニングなどの高頻度使用エリア。
✅ ウォルナット
- 特徴:高級家具にも使われる素材で、重厚で落ち着いた印象。
- 色味:ダークブラウン〜黒褐色。
- おすすめ用途:シックな書斎や寝室など。
✅ ヒノキ
- 特徴:柔らかく軽量、特有の芳香があり癒し効果も。
- 色味:白っぽい明るさがあり、時間と共に飴色に。
- おすすめ用途:和室・子ども部屋。
✅ スギ
- 特徴:柔らかいため傷つきやすいが、断熱性・吸音性に優れる。
- 色味:淡い赤みを帯びた優しい印象。
- おすすめ用途:素足で過ごす生活スタイルの家庭。
✅アカシア
- 特徴:硬質で耐久性が高く、反りや割れにも強い。施工性も良好。
- 色味:濃淡のコントラストが美しく、個性的な印象を与える。
- おすすめ用途:個性を出したいリビングやモダンな空間。ペットとの暮らしにも好適。
アカシアは比較的新しく注目されている無垢材のひとつで、見た目のインパクトと機能性を両立している点が魅力です。価格も比較的手ごろで、耐久性を重視したい方にも人気があります。
無垢材は硬さ・色味・価格やメンテナンス性や耐久性も異なるため、ライフスタイルやご家庭の状況(小さなお子様、ペットなど)に応じた選定が肝になります。また、リビング・寝室・子ども部屋など、部屋の用途に応じて最適な素材を選ぶという方法もおススメです。
塗装仕上げの違いを理解する|オイル vs ウレタン

無垢フローリングには「仕上げ方」にも種類があります。フローリングの“肌触り”や“見た目”は、仕上げ方法によって大きく変わります。無垢材では主にオイル仕上げとウレタン塗装が選ばれます。
- オイル仕上げ
- 木の質感をそのまま感じられる自然な仕上がり。
- 呼吸する素材の特性を生かせる。
- 定期的なメンテナンス(再塗装)が必要。
- ウレタン塗装
- 表面がコーティングされているため、汚れや水に強い。
- メンテナンスが比較的ラク。
- ツヤ感が強く、木の手触りはやや失われる。
オイル仕上げは自然派志向の方や経年変化を楽しみたい方に、ウレタン塗装は手入れの手間を減らしたい方におすすめです。毎日の使い方に合わせて、見た目以上に無理なく管理ができるものを選択するのが大切です。
メンテナンス性と耐久性|無垢材との付き合い方

無垢フローリングの美しさを保つためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。特にオイル仕上げの場合は、半年〜1年に一度の再塗装を行うことが理想的だと言われており、美しさを長く保つことができます。そして、日々の掃除は乾拭きが基本です。水拭きは避け、湿気対策を心がけます。正しい手入れを行えば、何十年も美しさを保つことが可能であり、長い目で見た場合には、修繕や交換の手間とコストを大きく削減することにもつながります。また、無垢材は傷がつきやすいですが、ヤスリで簡単に修復できるのもポイントです。表面を削って再塗装すれば、何度でも新品同様に再生できるのは、合板にはない魅力といえるでしょう。このように、愛着を持って大切に扱うことで、より快適な住空間を実現することができます。
最後に、無垢材は柔らかいためキズがつきやすいという最大のデメリットがあげられますが、それを「味」として楽しむのが無垢材の魅力でもあります。しかしながら、お子様が小さく、「傷があちこちについてしまうのは気になってしまう!」というご家庭等には、ダイニングテーブルの下やキッチン周り、お子様の遊び場等の傷が付きやすい場所に透明なフロアマットを使用することで傷が付くのを抑えることができます。このような工夫をすることで、改善することができますのでご安心ください。
基本の手入れ:
- 乾拭きを基本にし、湿度の高い日は換気を。
- 水拭きは避ける(膨張・収縮を招くため)。
- オイル仕上げの場合、半年〜1年ごとの再塗装で美しさを維持。
施工とコストの注意点|無垢材特有のポイントとは?
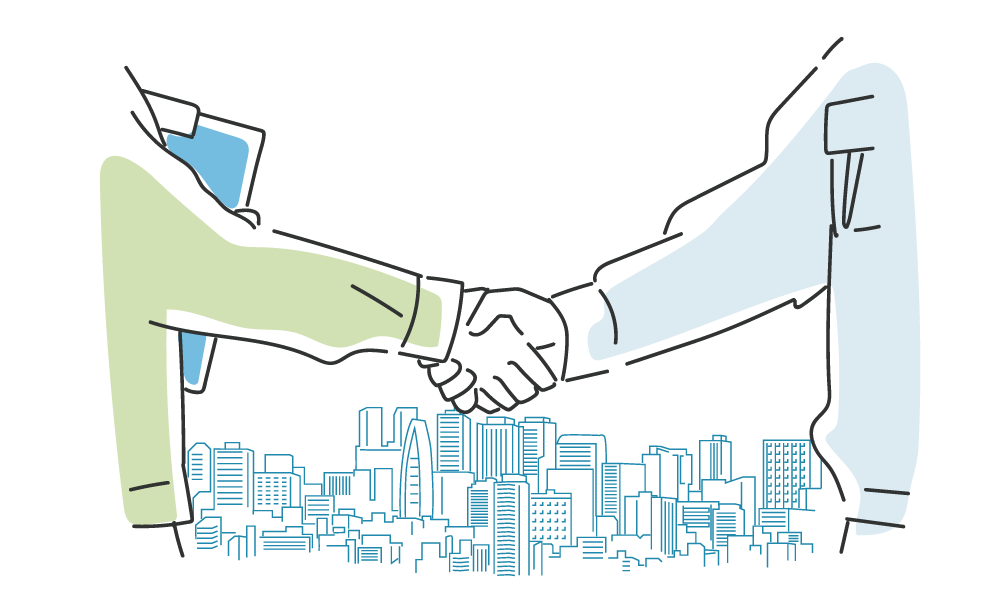
無垢フローリングは施工にも高度な技術が求められます。湿度による膨張・収縮が起こるため、それを見越した隙間処理や乾燥状態のチェックが必要です。そのため、施工業者の選定も非常に重要です。無垢材の取り扱いに慣れた専門の工務店や大工に依頼することで、施工後のトラブルを防げます。見分けるポイントは、施工会社の実績を確認するのがおススメです。完成見学会やモデルハウスをご見学の際は、全体の雰囲気だけではなく、仕上がりをチェックすると良いでしょう。
また、無垢フローリングの初期費用は合板に比べて1.5〜2倍になるケースが多いですが、10年、20年と張り替えずに使い続けられると考えれば、長期的にはコストパフォーマンスの良い選択と言えます。
施工時の注意点:
- 膨張・収縮対策として、隙間を計算した設計が必要。
- 現場の湿度や乾燥状況に応じた調整が求められる。
- 経験豊富な施工業者でないと、後から反りやきしみが出ることも。
まとめ|無垢フローリングは「暮らし方」で選ぶ
無垢フローリングは、自然の温もりと個性を与えてくれる魅力的な素材です。しかし、その良さを最大限に引き出すためには、素材や塗装、メンテナンス、施工といった複数の視点で選ぶ必要があります。また、傷が付きやすいといったデメリットもありますので、それを「アジ」として楽しむことができるか。そうでないかによって、無垢フローリングを最終的に採用するか。採用しないかが変わります。本コラムで紹介した5つの視点を参考にしていただければ幸いです。









