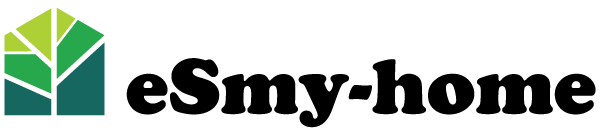

人生で最も高い買い物といわれる「マイホーム」。その中でも、自分のこだわりを反映できる注文住宅は、多くの人にとって憧れの選択肢です。しかし、自由度が高い反面、「気がついたら予算オーバーしていた」という失敗談も少なくありません。
本コラムでは、注文住宅で賢くコストを抑える方法と、最適な予算設定の考え方をご紹介いたします。
注文住宅でコスト削減意識が大切な理由

住宅の総費用は非常に大きな金額になります。そのため、住宅費用の計画が甘いと、これからの教育資金や老後資金、または日々の生活費を圧迫する要因になり兼ねません。だからこそ、適正な資金計画とコストの削減意識を忘れないことが大切です。
費用が予算を上回る原因
注文住宅を建設する際、当初の資金計画よりも予算が上回るケースが多々見られます。最も多い要因は、建築計画段階での予算取りの甘さです。次に多いのが、当初の計画から建築プランが変わってしまった、または面積が増加したことによって予算が上回ってしまうケース。最後に、設備や内装の仕様等を諦めきれず、予算が最終的に積み重なってしまったというケースがあります。
資金計画の重要性
資金計画を立てる際には、自分たちの予算を把握することが重要です。どのくらいの資金を用意できるのか。また、住宅ローンを利用する場合の返済計画についてもあらかじめ計画する必要があります。さらに、自分たちの収入や支出を見つめなおすことで、現実的な資金状況を把握することができます。総予算の把握ができたら、次に資金の内訳を定めます。土地購入費用、建築費用、内装費用、外構費用、さらにその他の諸経費に分けて計画を立てます。また、予期しない費用も考慮して、一定の予備資金を設けることが安心して家づくりを進めるうえで大切です。このように、資金計画は注文住宅を実現する上で欠かせないステップです。計画をしっかりと立てて、安心して理想の家づくりを進めていきましょう。
注文住宅のコスト削減方法
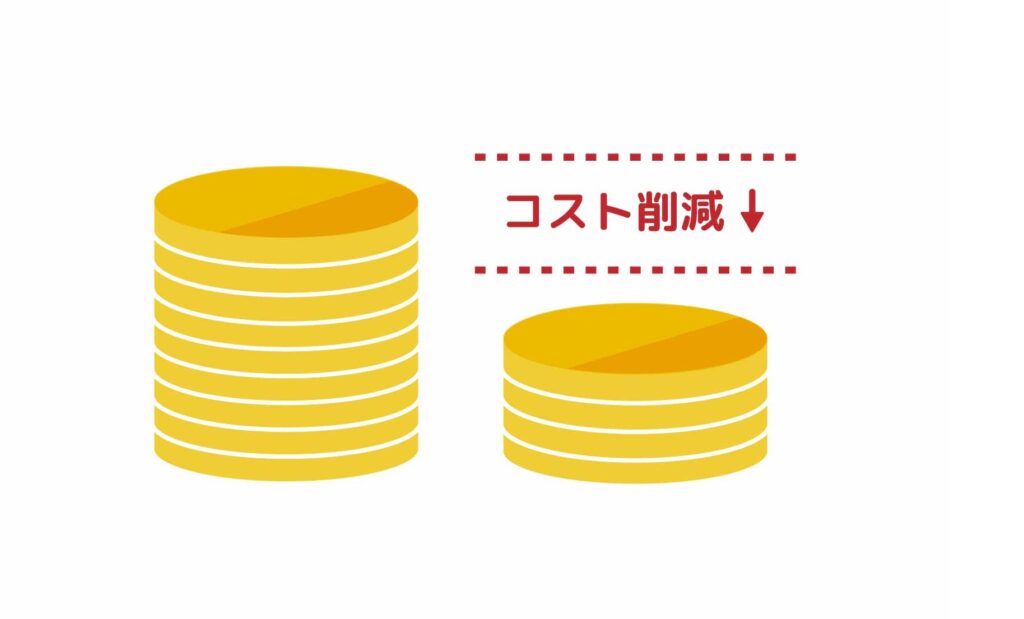
注文住宅を建てる際、コスト削減は大きな課題です。ご家族で何を大事にしたいのか。家づくりは「やりたいこと」の優先順位を整理することで、皆様の削減ポイントが異なります。ここでは、コスト削減の助けとなる方法について、ご紹介を致します。
建物の形状を見直す
同じ建築面積の建物でも形状によってコストが異なります。家の形状が複雑であればあるほど、施工に必要な時間や材料が増えるため、コストが嵩んでしまいます。そこで、同じ面積でもコストを抑えるためには、シンプルな形状を選択することがポイントです。例えば、四角や長方形といった基本的な形状は、施工が容易であり、無駄のない設計が可能です。こうしたシンプルなデザインは、資材のロスを最小限に抑え、工期を短縮する効果もあります。その結果、総合的なコストを大幅に下げることができます。さらに、建物の形状を単純化することで、後々のメンテナンスも楽になります。複雑な屋根や凹凸の多い外観は、修理や清掃が難しくなり、ランニングコストが高くなる傾向にあります。シンプルなデザインであれば、維持管理が容易で、長期間にわたってコストを抑えることが可能です。シンプルな形状だとデザイン性が失われるのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、シンプルに仕上げることは窓の配置や外壁の色、素材などの工夫次第で洗練された美しい印象にしあげることができます。このように、注文住宅における建物の形状を見直すことは、コスト削減だけでなく、機能性や美観にもプラスの影響を与えます。
設備と性能の見直し
選択した設備や建物の性能によって、初期費用だけでなく、長期的なランニングコストも変わります。そのため、長く住むことを想定した家づくりにおいては、住宅性能の選定が非常に大切です。たとえば、断熱材や窓の性能を見直すことで、冷暖房の効率が上がり、居住空間の快適さも向上します。また、エネルギー効率の高い給湯器や空調機器を採用することで、初期投資はやや高くても、長期的には費用対効果が期待できます。ただし、性能や機能が豊富な製品を選ぶ際は、自分たちのライフスタイルに合ったものを選ぶことが重要です。過剰な機能を持つ設備を導入すると、不要なコストが発生することもありますので、本当に必要な機能なのかを見極めることがポイントとなります。このように、設備と性能の見直しは、注文住宅においてコスト削減だけでなく、より快適な生活空間を実現するための重要なステップです。
後回しにできる項目を特定する
注文住宅を建てる際には、予算を抑えるために「後回しにできる項目」を特定することが重要です。この考え方を取り入れることで、初期費用を削減し、資金に余裕を持たせることができます。そのためには、家づくりの優先順位を明確にしましょう。どの部分が絶対に必要で、どの部分は後回しにできるのかを検討することが大切です。例えば、外部の仕上げや景観に関する部分は、一時的にシンプルなものを選び、将来的にゆっくりと手を入れるという選択肢があります。また、外構工事や庭の整備は、最初に行わなくても生活には大きな支障がないことが多いです。ですので、まずは建築本体を完成させ、その後、必要に応じて順次、手を加えていく方法が考えられます。さらに、内装の一部に関しても同様です。全てを高級な素材で揃える必要はありません。住み始めてからじっくりと改装を行うことで、費用を抑えられます。例えば、キッチンやバスルームの設備に関しては、使用頻度や利便性を考慮しつつ、後回しにできるアイテムから見直すことが賢明です。これらのポイントを抑えて、家づくりを進めることで、当初の資金計画に則った計画が可能になります。
コストダウンしすぎて後悔!?

コストダウンを追求するあまり、失敗を招くケースも少なくありません。コスト削減をする際には、短期的な視点だけではなく、長期的な視野も大切にする必要があります。
性能を落とし過ぎて後悔
住宅を建てる際、多くの方がコストを意識されると思いますが、性能を落としすぎることで後悔してしまうケースも散見されます。特に、家族が長く住むことを考えると、性能の重要性を軽視することは避けるのが得策です。コスト削減を重視しすぎて性能を下げると、夏は暑く、冬は寒い家になってしまいます。また、エアコン等の暖房や冷房機器の効きが悪い故に、光熱費も上がり、家計に負担がかかるという負のスパイラルが起きるリスクが高まります。それだけではなく、断熱性や気密性が低いと、結露が発生し易く、カビの発生を招く恐れも高まります。このように、住宅性能を軽視すると、後々大きな問題につながる可能性があるため、コスト削減を意識する際には、単に価格だけではなく、性能面でも慎重に考え、将来の安心を得るためのバランスを見極めることが重要です。
無理のない資金計画の立て方

自分たちの予算を設定し無理のない資金計画を立てることが大切です。ここで注意したいのは、あくまで無理のない範囲で設定することです。自己資金の割合を考慮し、無理な借り入れを避けるために、月々の返済額が家計に与える影響をシミュレーションしておくことが重要です。借入先の金利や返済期間によっても総返済額が変わりますので、様々なケースを検討することをおすすめします。
具体的なシミュレーション手法
まずは、全体の予算を把握するために、必要な費用をリストアップしましょう。具体的には、土地代、建物本体の価格、内装や設備にかかる費用、そして引越しや仲介手数料などが含まれます。これに加え、税金や保険料なども考慮することが必要です。次に、自分たちの自己資金を確認します。自己資金とは、自己資金比率とも呼ばれるもので、総費用の中で自己資金がどれだけ占めているかを示します。一般的には、自己資金の割合が高い方が、借入額が少なくなり、将来的な返済の負担が軽減されます。この点を踏まえて、無理のない借入額を算出すると良いでしょう。次に、金利や返済期間を考慮したシミュレーションを行います。ご自身で確認する場合は、銀行や金融機関のウェブサイトに、返済シュミレーターが提供されていることが一般的です。これを利用することで、借入額や金利、返済期間を入力し、毎月の返済額を簡単に計算できます。加えて、ライフプランも考慮に入れることが大切です。将来的に子どもが大学進学をする際や、老後の準備など、収支に変化が出るタイミングを考えて、それに応じた余裕を持ったシミュレーションをしておくことが大切です。これにより、安心して家づくりを進めるための基盤が整います。
まとめ
注文住宅を建てる際のコスト削減と最適予算設定の重要性について、これまでお話ししてきました。家を建てることは人生の中で大きな決断であり、予算管理はその成功のカギとなります。多くの方が憧れる注文住宅ですが、自由度の高さは、同時に「選択の責任」でもあります。正しい知識を持って、後悔のない家づくりを進めてください。









